
お知らせ
「場所」と「時間」どちらも自由。でもルールなしは危険信号

テレワークにフレックスタイム、今やこの組み合わせを導入している企業も少なくありません。特に事務職やIT系の業種では、「場所も自由」「時間も自由」が当たり前になってきました。
けれど、実はこれ、結構リスクの高い組み合わせです。
なぜなら、「場所の制約がない」と「時間の制約がない」をセットにするということは、会社の目が届かない状態を常態化させるということだからです。
「在宅勤務OK&フレックスタイム」自由さが生む盲点
- テレワーク=「どこで働くか」が自由
- フレックスタイム=「いつ働くか」が自由
つまり、「いつ・どこで働いているのか把握できない」という構図が自然とできてしまうのです。
社員の裁量が広がるのは良いこと。でも、それと同時に「働いているのかどうかの管理ができない」「働き方のルールが不明確」という事態になれば、それは経営側・管理側にとってはリスクでしかありません。
制度として導入する際は、「自由」を保障するだけでなく、どう管理するかというルールも必ずセットで設計する必要があります。
テレワーク×フレックスで最低限決めておきたいこと
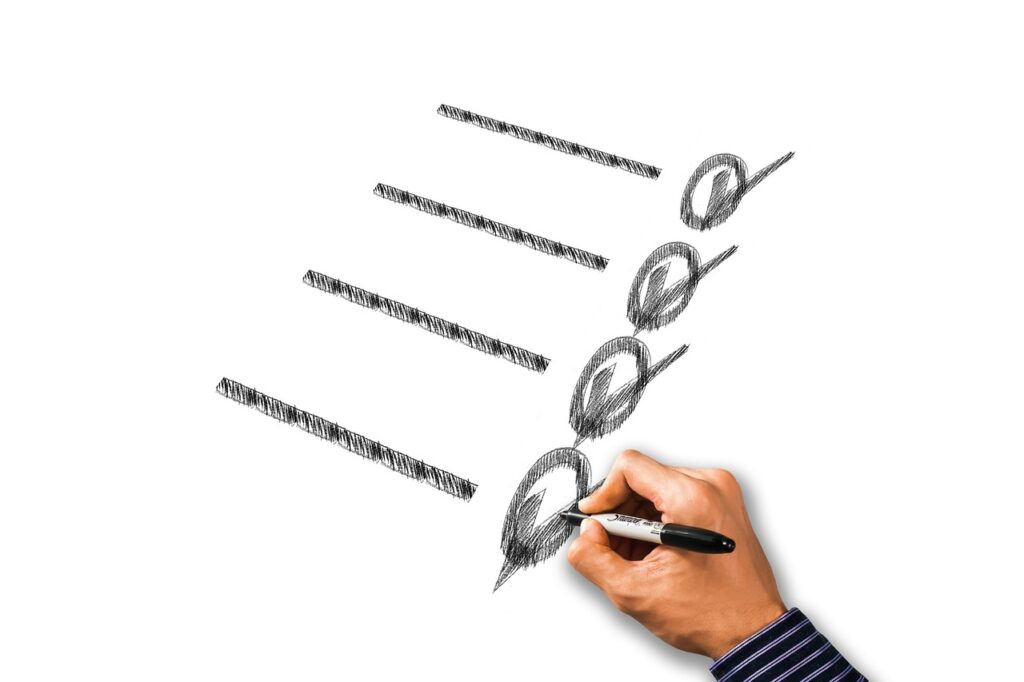
まず、「自由にさせてるからラクでしょ」と思ってる経営者や管理者の方ほど注意が必要です。
実は、決めておかないとあとで面倒になることがいくつもあります。
- コアタイムを設けるかどうか(在宅勤務時のみ設定する手もあり)
- フレキシブルタイムをどう設定するか(朝5時~夜22時?その根拠は?)
- テレワーク導入の背景は何か
└ 会社都合(スペースの都合・感染症対策など)か?
└ 社員のニーズ(育児・介護・通勤困難など)に応えたか?
この「いきさつ」は地味に重要で、手当の支給基準や光熱費の負担、出社命令の正当性などにも関わってきます。
さらに、以下の点も曖昧になりがちです。
- どんな状況でテレワークを認めるのか(希望制?業務内容次第?)
- 誰にテレワークを認めるのか(新卒社員も対象?一定の経験者のみ?)
- 会社が出社を命じる権限をどう担保するか(任意?命令できる?)
- テレワーク中の出退勤管理はどうするか(打刻方法?日報?在席確認?)
これらが曖昧なまま運用を始めると、問題が起きたときに「誰がどう判断するのか」が決まっておらず、トラブル処理に相当な工数を割くことになりかねません。
小さなルールこそ、大きな混乱を防ぐ
ルール作りというと、「面倒だな…」「柔軟性がなくなる」と感じるかもしれません。
でも、ルール=がんじがらめではありません。
むしろ、最小限のルールこそが、最大限の自由を守る防波堤になるんです。
たとえば、こんな工夫も立派なルールです。
- 在宅勤務のときだけ、コアタイム(例:10時〜15時)を設定する
- 前日までに在宅勤務の申請が必要、と義務づける
- 急なテレワークには上司の許可を必須にする
ポイントは、「現実の業務の流れに合わせてルールを作ること」。
社員全員がストレスなく働けて、会社も責任を持って労務管理できる状態を整えることが目的です。
「自由にしてるつもり」が一番危ない

「出社しなくていいし、好きな時間に働いていいよ」といった制度は、確かに社員にとって魅力的に映ります。
でも、その裏で何も決めていない自由ほど、企業にとって危ういものはありません。
- 管理できていないのに「働いた」とみなす
- 状況が曖昧なまま手当や責任が発生する
- トラブル時に判断基準が存在しない
このような事態を避けるには、導入前にきちんとした「設計」と「合意形成」が必要です。
「とりあえず柔軟にしておこう」は、のちのちの負担になって返ってきます。
ラクに運用するためのルールを、最初から用意しておくこと。それが、会社と社員を守る最大のポイントです。


