
お知らせ
働かないのも自由?フレックスタイム制での「欠勤ライン」

「フレックスタイムだから、今日は気分が乗らないので出社しません!」
…そんな社員がいたら、どう思いますか?
フレックスタイム制は「いつ働くか」はある程度任せられる制度ですが、「働かないこと」まで認める制度ではありません。
実はこの勘違い、制度設計時にルールを曖昧にしてしまった会社ほど起こりやすい問題です。
働く時間を決めるのは社員。でも働かない自由まではない
フレックスタイム制では、始業・終業時間を社員が自由に決められるのが特徴です。
でもそれはあくまで「労働時間の配分」の話。
働かない選択=欠勤の裁量まで与えたわけではありません。
たとえばこんなケースはいかがでしょうか?
「今日はのんびりしたいので、気が向いた時間に出勤しよう」…結果、気が向かず一度も出勤せず終了。
これは欠勤(更に言ってしまえば無断欠勤)です。
フレックスタイム制では、たとえ出勤時間が自由でも、就労義務がある日には働くことが前提です。
「0時間労働」までは許されていません。
遅れて来るのはOK。でも来ないはNG
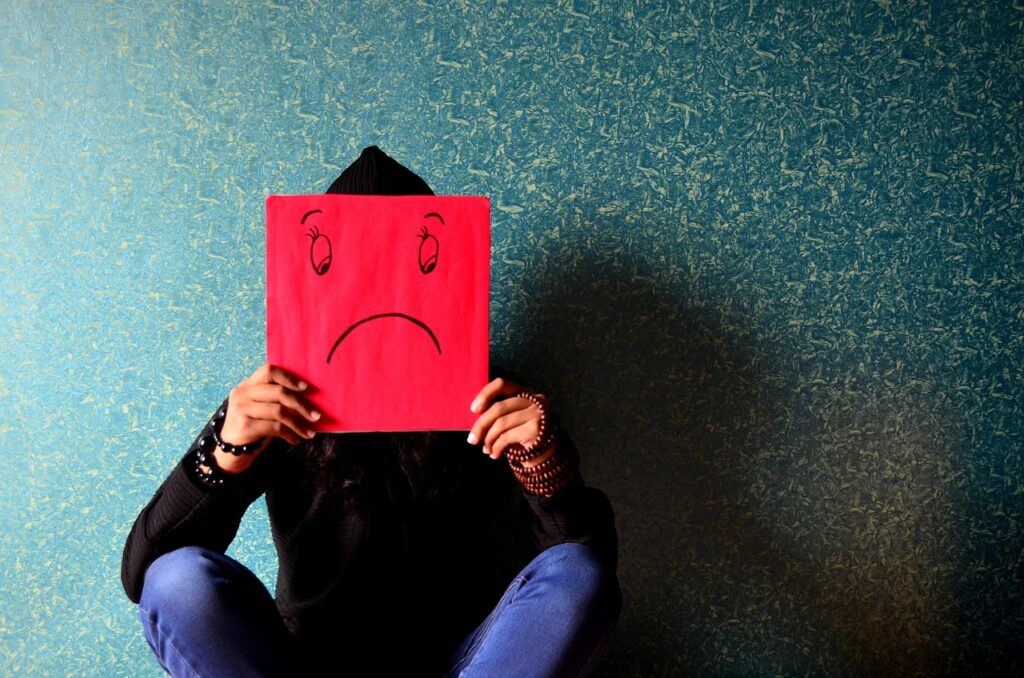
極端な例をもうひとつ。
社員が19時に突然やってきて、1時間だけ働いて帰る。
制度上、これはアリです。
でも、連絡もなしに急に来られても、現場としては正直困る。
管理者からすると「それで1日出勤扱い?」「日中に来ると思ってたけど?」とモヤモヤするはずです。
さらに厄介なのはこんなパターン。社員が20時に出社しようとしたけど、事務所が閉まっていて入れずそのまま帰宅。
ここで問題になるのが、フレキシブルタイムの設定と会社の設備状況の整合性です。
- フレキシブルタイムが「5:00〜22:00」になっている場合
⇒社員は労働可能な時間内に出勤しようとしていた。事務所が開いていないなら、会社側の責任となる可能性も。 - フレキシブルタイムが「8:00〜19:30」だった場合
⇒社員は労働時間外に来ようとしていたわけで、これは無断欠勤扱いにできる。
つまり、「欠勤かどうか」はタイムテーブルの設定と、会社の管理体制の整合性次第で判断が分かれます。
「じゃあ、欠勤っていつ決まるの?」
ここで素朴な疑問が湧きます。
フレキシブルタイムの終了時間まで出社するかもしれないとなれば、欠勤かどうかは22時まで判断できないの?と。
しかし、そんなことを毎日やっていたら、管理職も現場もストレスが爆発します。
だからこそ、「欠勤とみなす時間のルール」をあらかじめ決めておくことが重要です。
たとえば…
- コアタイム(例:11時〜15時)を設定していれば、「15時までに来なければ欠勤」
- フレキシブルタイムだけの場合は、「◯時までに出社しなければ欠勤とみなす」と明記
- 出社予定が決まってなければ、「午前中までに連絡がなければ欠勤」とルール化
こうした基準を定めることで、現場でも「今日は休みなのか」「午後に来るのか」が明確になるため、電話対応や他部署との連携もスムーズになります。
「自由」はルールのうえで成り立つもの
フレックスタイム制の本質は、「働く時間を自分で決める裁量がある」ということ。
でも、出社の有無すら会社が把握できない状態を許す制度ではありません。
- 欠勤扱いになるタイミング
- 勤務予定の連絡ルール
- 勤務時間外に来たときの扱い
このあたりを曖昧にしておくと、「自由な制度」のはずが、「誰が何してるかわからない制度」になります。
だからこそ、働く時間そのものは任せるにしても、連絡やコミュニケーションのルールはしっかり決める必要があるんです。
「何時に来てもいい」ではなく「来ることは前提」の制度設計を
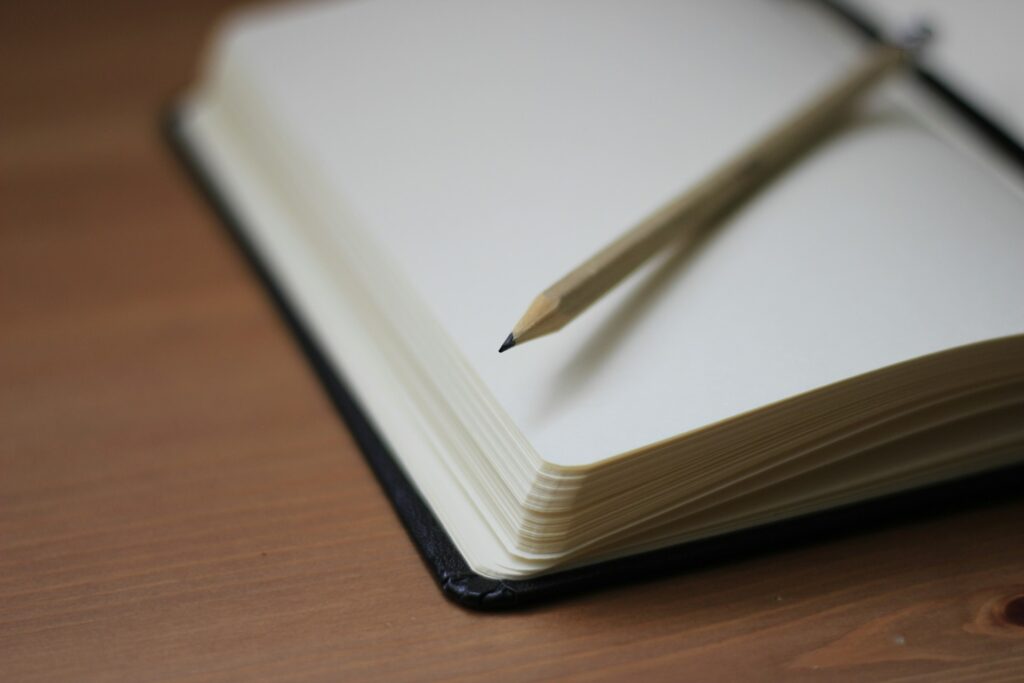
フレックスタイム制を導入する際、つい「自由に働ける」側面ばかりに目が向きがちです。
でも、社員の行動が会社から見えなくなることに対する備えをしていなければ、制度として成り立ちません。
- 何時までに出社していなければ欠勤か?
- 出社連絡はどのタイミングでするのか?
- 勤務予定と実績のズレをどう扱うのか?
こうした設計を怠れば、制度を悪用する社員が出てきたときに、会社として“防御不能”になります。
「自由を認める制度」には、「管理の仕組み」が不可欠。
ルールを先に整えておけば、あとで困ることはぐっと減ります。


